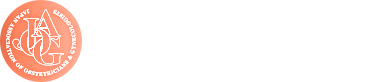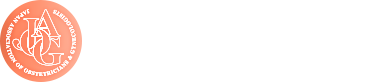10.事例から学ぶ:周術期管理・手術合併症
*POINT*
周術期管理における定型の指示やルーチンの対応が、ガイドライン・指針・教科書等に沿っているか、この機会に確認を!
今回は、術後の管理における過失が問題となった事例をご紹介します。
【事例】(実際の事例を簡略化し、一部改変を加えています)
患者Aは、B病院において右卵巣腫瘍に対し右付属器切除術を受けました。
医師は、手術直後、30分後、60分後、120分後、以後は定時(午前6時、午後2時、午後6時)にバイタルサインのチェックをするように指示し、指示に基づき看護師が血圧、脈拍、体温、血中酸素飽和度の検査をしました。
手術直後、30分後、1時間後、2時間後、6時間後のバイタルサインに異常はありませんでした。手術終了から術後6時間までの合計尿量は390mLでした。術後2時間後に患者Aが「痛くて我慢できない」「気持ち悪い」などと訴えたため、鎮痛剤と制吐剤の投与を行いました。
手術終了から約9時間後(前回のバイタルサインチェックから3時間後)に看護師が点滴の交換のために訪室すると、患者Aは心肺停止の状態であり、直ちに蘇生処置が行われましたが、死亡しました。
死亡後に行われた解剖では、死因は腹腔内出血で、骨盤腔の内壁に位置する子宮動脈の細い分枝が切断されていたことから、その動脈断端からの出血の可能性が高いとされました。
【争点と裁判所の判断】
患者Aの両親(患者Aの相続人)が原告となり、B病院に対し損害賠償を請求しました。原告側が主張した医師の過失は次の点です。
- 過失①:手術手技の過失
- 過失②:術後管理の過失(腹腔内出血を疑わせる全身状態の変化を発見して適切な処置を行うことを怠ったこと)
原告側が主張する上記の過失①及び②についての議論の前提として、まず、本件における腹腔内出血の態様(手術中からの出血が徐々に進行した緩慢な出血か?死亡の直前に結紮糸が滑脱したことによる急激な出血か?)が争いになりました。裁判所は、解剖を行った医師の鑑定書、専門医の意見書、尋問結果を主な根拠として、手術時から緩慢な出血が持続した(=手術中に子宮動脈分枝が切断されたことを認識せず、結紮しなかった)、との事実を認定しました。
次に、上記の過失②について、医師らによる術後のバイタルサインのチェックの指示が不十分であったこと、実際に十分なバイタルサインのチェックがなされなかったこと、術後6時間の合計尿量の記載があるのみで時間尿量が確認されていないなど全身状態の観察が不十分であったこと、特に術後6時間以降にバイタルサインのチェックがされなかったことが指摘され、術後管理の過失(過失②)があると判断されました。
その上で、裁判所は、死亡直前に発生した急激な出血ではなく、当初から緩慢な出血が続いていたのであるから、術後の安全管理を適切に行い、腹腔内出血を疑わせる全身状態の変化を発見して適切な処置を行っていれば、患者Aが助かった可能性が十分あったとして、手術手技の過失(過失①)について論じるまでもなく、医師らに適切な術後管理を怠った過失(過失②)があり、医師らは責任を負うと判断しました。
【解説】
術中や術後の経過における過失が問題となる事例では、多くの場合、過失①のように手術手技の過失が争われます。しかしながら、解剖学的なあるいは病態等による個体差など、手術には不確実性が内在することなどから、明確な証拠がある場合を除いて、裁判における手術手技の過失についての判断は困難であることが少なくありません。本件でも手術手技の過失(過失①)が争われましたが、裁判所は、この点についての判断を避け、術後管理の過失(過失②)についてのみ判断しました。このように、手術手技の過失に比べると、術後管理の過失を立証するハードルは低いことが多いと考えられます。
本件では、術後管理の過失(過失②)について判断するに際し、具体的にどのような術後管理をすべきだったか?適切な術後管理とは何か?を判断するための証拠として、「産婦人科研修の必修知識」(日本産科婦人科学会)を含む複数の文献・教科書等が用いられました。そして、これらの記載からすれば、術後24時間以内の管理として、バイタルサイン(脈拍、血圧、尿量、体温)は安定するまで30分ごとに測定しその後は2~3時間ごとに測定、尿量は40~50mL/時以上を保つようにすべきであった、という基準を示した上で、本件では、術後6時間以降のバイタルサインや時間尿量の測定の点においてこの基準を満たしておらず、術後管理に過失があったと判断しました。
【本事例から学ぶこと】
本件のように、手術手技の過失ではなく、術後管理の過失が認められたことによって医師らの責任が認められるケースは少なくありません。本件の裁判所の判断には、様々な感想やご意見をお持ちになったのではないかと思いますが、この機会に、普段の臨床で用いている定型またはルーチンで行っている周術期の指示や対応などについて、改めて見直すきっかけにしていただければと思います。
本事例では、医師が行なった「手術直後、30分後、60分後、120分後、以後は定時(午前6時、午後2時、午後6時)にバイタルサインのチェック」という指示は、この病院における定型の指示であったとしても、複数の文献・教科書等に示された術後管理と比較すると不十分なものであると判断されました。このように、たとえ、自身の医療機関ではそれまで問題が起きておらず慣例的・経験的に行なってきた方法であったとしても、それだけでは医学的に適切であることの根拠としては不十分であり、過失が否定されるわけではありません。これまでこのシリーズでも、紛争事例におけるガイドライン等の扱われ方に触れてきましたが、普段の臨床で用いている定型の指示やルーチンの対応などが、信頼度の高いガイドラインやそれに準じる指針・教科書等に示されていることに沿ったものになっているか、この機会に改めて確認してみてはいかがでしょうか。そして、もしガイドライン等と異なった内容になっている場合において、その理由について医学的根拠に基づき合理性のある説明ができないのであれば、修正を検討すべきでしょう。