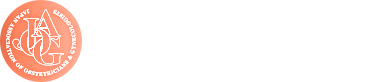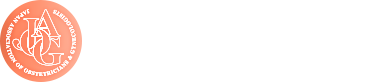9.事例から学ぶ:婦人科疾患の診断
今回は、婦人科疾患の診断の場面での過失が問題となった事例をご紹介します。
【事例】(実際の事例を簡略化し、一部改変を加えています)
患者Aは、子宮筋腫の診断で、経過観察のため半年に1回程度Bクリニックに通院し、医師Cによる経膣超音波検査を含む診察を受けていました。
通院開始から約3年が経過した頃に、下腹痛、腹部膨満感等を自覚してBクリニックを受診しました。医師Cが、患者Aを診察したところ、それまで経過観察していた子宮筋腫とは別に腫瘤像を認めました。医師Cは卵巣腫瘍の可能性もあると考え、カルテには「卵巣腫瘍の可能性もあり」と記載したものの、さらにMRI等の検査を行った上でなければ患者Aに卵巣腫瘍の可能性があると述べることはできないと考え、「子宮筋腫が大きくなっている。」と説明しました。紹介状に「経膣超音波検査で急速に増大する子宮筋腫を認めます。挙児希望あり筋腫核出術を希望されています。」などと記載して、D病院へ紹介しました。
D病院において、経膣超音波検査・骨盤MRI検査等を行い、紹介受診から約2週間後に卵巣腫瘍の診断で開腹手術が行われました。術中迅速病理検査で卵巣癌と診断され、両側付属器切除術+子宮全摘出術+大網切除術+骨盤・傍大動脈リンパ節郭清が施行されました。卵巣癌IIIC期の診断で術後に化学療法が行われるも、約1年後に死亡しました。
【紛争の経過と争点】
患者Aの死亡後、夫(患者Aの相続人)が原告となり、Bクリニック及び医師Cに対し損害賠償を請求しました。
原告側の主な主張は次の2点です。
- ①約3年間の通院中において、卵巣腫瘍を早期に発見することができなかったことに過失がある。
- ②患者Aが下腹痛、腹部膨満感を自覚してBクリニックを受診したときに、卵巣腫瘍を疑わず、子宮筋腫と誤診したことに過失がある。
【裁判所の判断】
裁判所は、上記①②について、それぞれ次のように判断しました。
- ①本件のような進行の早い卵巣癌では、早期に発見することが可能であったとは言えない。
- ②医師Cは、内診及び超音波検査によって子宮筋腫と卵巣腫瘍の双方の可能性を疑っていた。
また、卵巣腫瘍の疑いを抱きつつも子宮筋腫と診断して高次医療機関を紹介することは誤診とまでは言えない。
このように本件では、診断の遅れ(子宮筋腫フォロー中に卵巣癌を早期に発見できなかったこと)や誤診(卵巣腫瘍を子宮筋腫の増大と誤診したこと)があったか否かが主な争点となりました。裁判所は、カルテを詳細に検証し、専門医の意見や医学文献などを参照して、医師Cに過失はないと判断し、原告の請求を棄却しました。
【本事例から学ぶこと】
①本件では、3年間の経過観察期間中のカルテに貼付されていた超音波検査の写真を検証するなどして、この期間において卵巣癌を発見することはできなかったと判断されていますが、この裁判所の判断は紙一重だった可能性があります。
日常診療において、良性疾患の治療やフォロー等のために定期的に通院している患者の診察では、良性疾患の症状の推移や治療の要否、悪性所見の有無等にも注意しながら慎重に経過を観察されていることと思います。
ところが、せっかくこれらの点に注意しながら慎重に経過観察していても、たとえば漫然と画像や検査結果を記録に残すだけでは、慎重に経過観察していることを客観的に示す資料としては不十分です。
簡単なコメントで良いので、なぜその時点で経過観察可能と評価したのかがわかるような記述を残すことで、この点がクリアになります。
何より、病態を整理し方針を決定するためにも有用ですし、副次的には、万が一紛争化した場合にも有用な資料(証拠)となります。
②次に、経過観察中に何らかの変化があったとき(治療が必要となったり悪性を疑ったりした場合など)は、慎重かつ迅速にその後の精査加療が行われるべきですが、その際の患者への説明や対応次第では、本件のように紛争化してしまうことにも注意が必要です。
本件では、医師Cは卵巣腫瘍の疑いがあると思いながらも精査後でなければ何も説明するわけにはいかないと考えて、卵巣腫瘍については言及せずにいたのですが、残念ながらかえって患者の不信を助長することになったとも言えそうです。
患者の立場に立ってみると、子宮筋腫として半年に1回通院している途中に「子宮筋腫が大きくなっている」とのみ説明を受けたわけですから、卵巣腫瘍ましてや卵巣癌などとは全く思っていません。
紹介先で突然、卵巣腫瘍だと説明を受け、さらには進行した卵巣癌と診断されたことから、医師Cが誤診したと思うのも無理はないようにも思えます。
本件では「卵巣腫瘍の可能性あり」とカルテに記載されていたことが重要なポイントになって、裁判では、医師Cは誤診したのではなく子宮筋腫の増大または卵巣腫瘍を疑ってD病院を紹介したという事実が認定されました。
ここでも、カルテ記載がいかに重要であるかがわかります。
しかしながら、そもそも、卵巣腫瘍を疑うような所見を認めたのであれば、精査前であり「疑い」であることも含めて同時点でわかっていることや見込み等を患者Aに説明していれば、このように紛争化することは避けられたのではないかと推測されます。
もちろん、むやみに患者の不安を煽るのは不適切であり、何でもそのまま説明すれば良いわけではありません。
各患者の病態や理解度等に合わせて、どこまで説明するかを個別に検討すべきですが、患者の受け止め方に配慮した説明が、紛争予防にもつながるものと思われます。
次回は、周術期管理や手術合併症に関連する事例を扱う予定です。