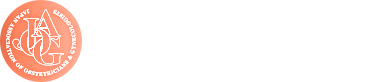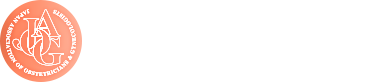第一回:産婦人科診療で患者を痛がらせないことの重要性とそのコツ ~産婦人科外来診療・小手術時の麻酔のポイント~
順天堂大学医学部産婦人科学講座名誉教授・客員教授
愛育会愛育研究所所長
竹田 省
問 あなたにとって“痛み”の思い出は?
答 痛みや恐怖体験は心的外傷後ストレス障害(post traumatic stress disorder:PTSD)のきっかけになります。私自身子供の頃、抜歯の際の局麻の痛みは、その後歯科に行くたびに思い起こされ、ドリルの音は恐怖、不安を引き起こし、知らず知らずに体が硬くなり全身汗をかくことになります。医師となり、初めて長期間受け持った患者が亡くなり、霊安室で口惜しさと無力さで涙したことはその後の見送りの際には、いつもよみがえります。
最近の歯科診療は驚くほど進歩しています。局所麻酔する場所にまず表面麻酔をし、極細針を用い、痛みは全くありません。我々産婦人科医は歯科医が努力して改善してきた診療をどう思っているのですか? 我々の診療はこれでいいのですか?と自問しています。
問 産婦人科診療現場にあふれる“痛み”とは?
答 分娩室や陣痛室に行けば妊婦さんはうんうんうなっています。会陰切開や裂傷縫合時に局所麻酔が十分効いていないうちに処置を始めたり、効きが悪くても追加麻酔せずに縫合することもありました。子宮内の胎盤遺残確認や胎盤用手剥離も無麻酔が多く、小さな裂傷なども無麻酔で縫合したこともありました。内診やクスコ診、経腟プローブ挿入自体が痛みの原因となります。子宮内膜細胞診や組織診の検体採取や生検、Intrauterine Device(IUD)やIntrauterine System(IUS)の挿入抜去、採卵など無麻酔で行う処置や検査も多くあります。
医療従事者も患者の不安、恐怖はもちろんのこと診療に関わる痛みの知識を持っているにもかかわらず、知らず知らずのうちに痛みを我慢させ日常診療を行ってきたのではないでしょうか? その臨床現場に慣れ“女性は痛みに強い!? 女性は少しの痛みに耐えられる”という間違った考えを持って診療を行っている医療従事者がみられるのも事実です。
問 診療時の“痛み”に対する欧米との違いは?
答 前述のMVAキットの米国の使用説明書には、子宮腟部鉗子を使用する際、把持部に局所麻酔をすると書かれています。また、傍頸管麻酔の局麻下で流産手術を外来で行うと記載されていました。傍頸管麻酔は、ラミナリア挿入時や子宮内操作、採卵などにも使用されています。アメリカ在住者に無麻酔で子宮内膜採取した時、終了してから「この痛みはアメリカなら訴訟になるかもしれませんよ」と言われたこともあります。
国際医療機能評価(JCI)認定では、患者の疼痛評価は初診時から必須であり、痛みがどの程度でその後どうなったか必ず追跡し、カルテ記載することが重要です。それほど痛みの評価、対応が重視され、大事な医療評価指標となっています。診療では身体的のみならず精神的苦痛をとり除き、病気の苦しみから解放することが医療の原点です。診療そのもので痛みを引き起こし、それを我慢させることが忙しいからと言って正当化されるのでしょうか? 医療者は時間の余裕がないと言い訳し、診療そのものの苦痛を軽減する努力を怠っていいのでしょうか?
問 “痛み”に敏感な人はどんな人ですか? どんな対応が必要ですか?
答 痛みは主観的なものであり、個々でその感受性が著しく異なることは臨床上よく経験することです。虐待被害者やPTSDなどトラウマを持っている人は恐怖心や不安を最初から強く持っており、疼痛や未体験のことに対して敏感に反応します。流産手術時の検討では、痛みの増悪因子は、若年者、少ない妊娠既往、月経困難症など痛みに関連する疾患を有する、不安が強い、うつ病既往などが挙げられています。
その対応は、痛みをできるだけ取り除き、不安や恐怖を事前に十分説明し和らげることが大切です。また、診察や処置、手術を施行する際は、説明しながら行い、極力安心させることがポイントとなります。その説明、コミュニケーションも型どおりではなく、信頼を作り上げ、「傾聴と共感」に基づく対応、コミュニケーションスキルが重要で、医療安全にも通ずる重要なものです。痛みや訴えをよく聞き、共感するカウンセリングとも言えるスキルです。
問 “痛み”を我慢させることはどんな影響がありますか?
答 分娩時の激烈な痛みや恐怖体験が、PTSDや分娩恐怖症(tokophobia)を引き起こすことは知られており、二度とお産をしたくないと思う人が6~14%存在します。このような人は、産後うつ病、不安障害やボンディング障害などの頻度が高く、育児困難など長期的な母児相互関係の障害が問題となることがあります。また、経腟分娩や帝王切開術後の疼痛体験や創部の痛みと産後うつ病の関連を指摘する数多くの報告もあります。このように分娩時の身体的痛み体験や流産や死産、児の奇形や脳性麻痺など心の痛み体験がPTSDや精神的問題を引き起こし、育児に悪影響を及ぼすことを我々医療従事者は常に念頭に置く必要があります。婦人科領域でも同様で生涯PTSDや心の傷として悩まされることになります。
口腔内や咽頭部および子宮周囲部の知覚神経枝は迷走神経を経由して伝達されます。疼痛刺激などによって迷走神経反射が惹起されショックに陥ることが知られています。歯科領域では以前は局麻時の疼痛刺激による心停止が問題になっていましたが、表面麻酔や極細針の使用により激減しています。同様に子宮腔内操作や頸部の処置や手術、傍頸管麻酔などの痛み刺激でも迷走神経反射が起こることがあり、その対応や防止対策に習熟する必要があります。
問 局所麻酔のコツを教えてください
答 外陰・会陰部や腟、子宮の局所解剖、特に血管や神経の走行を熟知する必要があります。用途によって表面麻酔、浸潤麻酔、伝達麻酔(傍頸管麻酔、陰部神経麻酔など)を使い分けることが重要です。また、使う局所麻酔薬の性質、投与量、作用時間、極量など知っておく必要があります。血管穿刺や迷走神経反射、局麻薬中毒の対応にも精通する必要があります。長時間作用性のエピネフリン添加薬は通常必要ないですが、使用する場合は血圧などモニターすることが大切です。
表面麻酔は、局麻薬を綿球やガーゼに浸み込ませて使用したり、ゼリーやスプレータイプのものもあります。粘膜部分の処置や生検、浸潤麻酔の刺入部の麻酔に使用できます。頸管拡張や子宮内操作、採卵をする場合などでは傍頸管麻酔が使われます。広範な会陰裂傷、Ⅳ度裂傷縫合には陰部神経麻酔が有用です。外肛門括約筋が損傷したような場合には括約筋弛緩が得られるため縫合不全も少なくなります。
局所麻酔は作用発現まで2、3分から数分かかるので効果を確認して処置、手術を開始します。患者が覚醒しており、緊張や不安を助長するのでスタッフとの会話には十分配慮します。これから何をするのか、今何をしているのか、痛くないか、麻酔が効いているいるかどうか、気分が悪くないかなど患者と話しながら処置や縫合を行います。不安な患者を安心させ、痛みに細かく配慮する姿勢とともに会話による患者サポート“verbal support”が重要です。医師のみならず介助者にもこの姿勢を徹底させます。子宮頸部に集中する迷走神経に作用する傍頸管麻酔は迷走神経反射を来しやすいので注意します。患者との会話の中から迷走神経反射やアナフィラキシー、局麻薬中毒などの初期症状に気付くこともよくあります。
問 技術指導はどのように行えばいいのですか?
答 局所麻酔や産婦人科処置、小手術などの技術指導は、いままで各研修病院に任されていました。特に産科技術指導は修練施設の伝統などによって大きく異なり、全く研修できない技術もあります。Royal College of Obstetricians and Gynaecologists(RCOG)では標準化した産科技術指導を定期的に行っており、修練医の必須の研修項目となっています。ようやく日本でも種々の学会時に少しづつ産婦人科に関連する技術トレーニングやハンズオンセミナーが開催されるようになってきました。今後、学会や医会などで標準化された技術トレーニングができるようになってほしいものです。局所麻酔についても研修用のvideo教材やトレーニング用の模型も開発されており、傍頸管麻酔や陰部神経麻酔などの伝達麻酔も含めた技術指導を、各施設あるいは研修の場で行っていくことが必要です。On the job trainingでは、患者さんに不安や恐怖を与えないよう十分に言動に配慮し教育することが大切です。
問 Patient centered careとは?
答 患者中心の医療とは、「病気を見ていて患者を見ていない」などの批判を受けて医師や病院中心の医療ではなく、個々の患者、家族のニーズや好みに合わせて医療を提供するものです。特に緩和ケアや癌治療の分野から展開され、今日様々な医療分野でもその考えが導入されています。その推進には患者、医師間のコミュニケーションが重要であり、信頼関係を築く高いスキルが望まれます。
診療ガイドの実践は、標準的なレベルを知り、診療の均てん化や医療のレベルアップに貢献してきました。しかし、このレベルで診療していればそれでよいとなっていないでしょうか? もっと改善することはないでしょうか? 特に「痛み」は身体的なものであれ精神的なものであれ本人にしかわからない自覚的な感覚です。感じ方がそれぞれに異なるものに対して画一的に対応すること自体困難と言えます。良好なコミュニケーションを保ち、個々にそれぞれ対応する“痛がらせない”診療は、“Patient centered care”の一環として医療界全体で取り組む必要があると思われます。